石上神宮|奈良|国内屈指のパワースポット!七支刀のお守りに、蘇り・起死回生の霊力を込める!

奈良県天理市、日本最古の街道「山の辺の道」の北側に位置し、龍王山と布留山の西麓に鎮座する石上神宮。日本書紀によると、伊勢神宮とならんで日本最古の神宮号を冠した神社とされる古社だ。
延喜式神名帳には「石上坐布都御魂神社」と記述さる名神大社であり、二十二社の中七社に列せられる、霊験あらたかな神社である。
主祭神は、神宝に宿るご神霊。中でも十種神宝の霊力は死者をも蘇らせることができるという。
石上神宮について
石上神宮 概要
- 所在地 奈良県天理市布留町384
- 電話番号 0743-62-0900
- 主祭神 布都御魂大神、布留御魂大神、布津斯御魂大神
- 創建年 崇神7年(紀元前90年ごろ)
- 社格 名神大社・二十二社・官幣大社・別表神社
- 公式HP http://www.isonokami.jp/
石上神宮 アクセス
MAP
最寄り駅
- JR桜井線・近鉄天理線「天理駅」徒歩30分
- バスに乗って「石上神宮前」バス停下車という手もあるが、本数が少ない
駐車場
- あり(無料)
石上神宮の創建
神宮の略記によると、
10代崇神天皇の勅命により、饒速日命の御子であり物部氏の祖とされる宇摩志摩治命の6世孫伊香色雄命が、宮中で祀られていた韴霊剣と十種瑞宝を布留の高庭に移して奉祀したのが始まり
としている。
以来、石上神宮は神宝としての武器を収める武器庫とさた。各地で服従させた部族から押収した神宝としての武器を収容するのである。戦利品倉庫のようなものであろう。そんな武器庫の警護を任されたのが、朝廷の警察機関であり軍事氏族であった物部氏。そういうことから、石上神宮は物部氏の総氏神とされたようだ。
石上神宮の祭神
主祭神は以下の通り。神の持ち物に宿る神霊となっている。
布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)
布都御魂剣(ふつのみたまのつるぎ)に宿る神霊。
布都御魂剣とは、武甕雷神(たけみかづちのかみ)が、国譲りの時に持っていた剣。神武東征の際、熊野で苦戦した神武に高倉下を通じて遣わされた。国土の平定に使われた剣といえよう。
布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)
十種瑞宝(とくさのみずたから)に宿る神霊。
十種瑞宝とは、饒速日尊が天下る際に天神から授けられたとされる神宝。死人を蘇らせる霊力を持っているといわれている。
布津斯御魂大神(ふつしみたまのおおかみ)
天十握剣(あめのとつかのつるぎ)に宿る神霊。
須佐之男尊が八岐大蛇を退治したときに使われた剣といわれている。
石上神宮の配神
配神に、宇摩志摩治命、五十瓊敷命 、白川天皇、市川臣命 が祀られている。
宇摩志摩治命(うましまじのみこと)
神武天皇に十種神宝を譲り、また、これを使った呪術と物部部族の軍事力でミカドの治世に貢献した人物。その後の物部氏の繁栄の礎を築いた。
五十瓊敷命 (いにしきのみこと)
垂仁天皇の御子である。皇位にはつかず、たくさんの剣を造っては石上神宮に納めた皇子とされている。よって石上神宮の神宝は、次第に五十瓊敷命が掌握することになる。この権力が後に物部氏の手に渡ることになる。
白川天皇
石上神宮を崇敬した天皇である。宮中の神嘉殿を拝殿に寄進した。
市川臣命(いちかわおみのみこと)
石上神宮社職の始祖である。その子孫は「布留宿禰」と称し、物部氏に副って祭祀を司った。
御本地(禁足地)
拝殿の奥に御本地(禁足地)がある。ここは2000年の間、いかなる人も入ってはならない場所とされてきた。というのも、御本地(禁足地)の中央に主祭神のご神体が埋斎されていたからだ。
明治時代になって、国の許しを得た大宮司さんが初めて御本地(禁足地)を掘り起こしたところ、やはりそこには、ご神体の剣が埋斎されていたそうだ。
当然ながら、一般参拝者はその場所すら見ることができない。
石上神宮の御利益
十種瑞宝に宿る神霊のご神徳により、起死回生の御利益を頂きたい。もちろん、健康長寿・病気平癒の御利益も頂けるであろう。そのほかにも除災招福・百事成就の守護神として信仰を集めている。
石上神宮 参拝記録
公共交通機関では、なかなかアプローチしにくい立地である。天理駅から徒歩で30分。バスに乗ると10分だが、3~4時間に1本しかない。バスの利用は非現実的であろう。
車でのアプローチであれば、天理教本部の近くに案内板が出ている。山に向かって進むと石上神宮がある。
駐車場は無料。きれいなトイレも完備されている。駐車場は鳥居と本殿エリアの中間にあるため、一旦徒歩で駐車場から出て、あらためて一の鳥居から訪問しよう。
大鳥居

さあ、表の鳥居に回り込む。鳥居から入場するのが筋ということもあるが、鳥居をくぐると空気が変わるという、神社参拝の醍醐味を味わいたいからである。
かの聖徳太子がこの鳥居をくぐったときに、「ただならぬ気配を感じる」とおっしゃった
という逸話も残っているからして、是非味わって頂きたい。
ご覧の通り立派な鳥居である。材木の一つ一つが太い。そして、なんとも言えない照りがある。そして扁額が極めてデカイ!
とにかく重厚で存在感がハンパない鳥居だ。
近づいていくと、鳥居をくぐる前から冷気が迫ってくる。シャキっと目が覚める感覚だ。活力アップ間違いなし!
東天紅

先に進もう。ニワトリがたくさん飼われている。神様の使いである。
このニワトリは東天紅。中華料理店のような名称だが、この鳥は天然記念物。
長鳴き鳥の一種で、夜明けの東の空が紅に染る頃に天性の美声で謡うところから命名されたという。
私が入っていくと、コケコッコーと歓迎ムード。ニワトリの鳴き声を聞くと良いということであるからして、いい感じだ。
次のページもご覧ください!
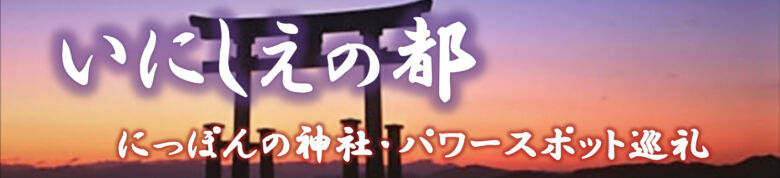
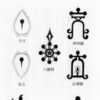








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません