四天王寺七宮 厄払い!北辰北斗パワーで封印するものとは、いったい何なのか!

過去の記事、四天王寺|大阪|四天王寺は巧妙に隠された神社であった。で、
- 中心伽藍の転法輪石の意味するところがわからない
- 四天王寺と七宮の関係が、もうひとつはっきりしない
という課題を自らに科した。今回は、この問題について自分なりの、現時点での結論を述べたいと思う。異論はあると思うが、ご容赦願いたい。
もし、四天王寺|大阪|四天王寺は巧妙に隠された神社であった。をお読み頂いてない方は、是非ともお読み頂きたいと思う。
四天王寺七宮について
四天王寺七宮は、聖徳太子が四天王寺を建立した際、その鎮守として同時に創建した、あるいは指定したとされる七つの神社のことを指す。いずれも大阪市天王寺区にある。
七宮それぞれの概略を、北から順に、反時計回りでご紹介しよう。
上之宮神社(大江神社に合祀)

摂津国名所図会に見える欽明天皇神祠のことと思われる。同じ境内に天照大神を祀る上野王子社があるという。同じ七宮の一つである大江神社に合祀された。
旧鎮座地は、近鉄大阪線・奈良線の上本町駅から徒歩10分ほど、高校野球で有名な上宮高校の南東あたりか。上宮ハイツの玄関横の植え込みの中に石碑が立つ。
大江神社

四天王寺前夕陽丘駅から徒歩3分。縁結びで有名な愛染さんのとなりにある。主祭神は豊受大神。
明治40年に、同じ七宮であるところの土塔神社、上之宮神社、明治41年には同じ七宮の小儀神社を合祀した。伊勢神道によると、豊受大神は天御中主神と同一神とのことである。
堀越神社

JR天王寺駅から徒歩10分。一生に一度の願いをかなえてくれる神社として売り出し中の神社である。こちらの主祭神は崇峻天皇。蘇我馬子に謀殺された天皇で、聖徳太子の叔父にあたる。叔父を偲んで聖徳太子が建立したと伝えられている。しかし、、、江戸時代末期の古地図では「敏達天皇社」となっていたが、なぜだろう。
いずれにしても、こちらで注目すべきは、「ちんたくさん」太上神仙鎮宅七十二霊符尊神である。星神を祀っており、お札やお守りの元祖とされている。よって最強の護符と言われているのだ。そして、さらに興味深いことは、七夕の星まつりの際には大真西王母須勢理姫命を勧請して復活再生を願うとある。
土塔神社(大江神社に合祀)

四天王寺南大門の南にあったとされる。詳細な場所は特定されておらず石碑などもない。
明治40年に同じ七宮のひとつ大江神社に合祀された。主祭神は須佐之男尊。江戸末期の古地図には「牛頭天王」と記載されている。
河堀稲生神社(こぼれいなり)

JR寺田町から徒歩7分。第十二代景行天皇の時代に稲生の神を祀ったのが始まり。
聖徳太子が四天王寺を建立した際に社殿を造営し、叔父の崇峻天皇と宇賀魂大神を合祀した。摂社の若宮八幡宮には應神天皇、仁徳天皇が祀られ 配祀として和氣清麻呂が祀られている。
この和気清麻呂、奈良時代から平安時代初めに活躍した官人である。「河内摂津の界に川を堀り堤を築き、荒陵の南より河内川を導き、西の海に通せんとして、当社に祈願した」らしい。気骨ある人だったらしい。
和気清麻呂を主祭神とする神社が京都御所の西にある。こちらもいずれレポートしたい。
河堀稲生神社|四天王寺七宮|伏見稲荷よりも古くから稲の神を祀る神社は怨霊封じの神社でもあった!
久保神社(くぼ)

天王寺区勝山2丁目、寺田町野球場の北に面している。
祭神は天照大御神、須佐之男尊、伊邪那岐尊、伊邪那美尊、宇賀御霊神。摂社の「願成就宮」は、物部守屋を祀っているものと推察する。
小儀神社(大江神社に合祀)

四天王寺東門の東にあったとされる。こちらも明治41年に大江神社に合祀された。主祭神は須佐之男尊。こちらも江戸末期の古地図には「牛頭天王」と記載されている。
ハイツ天王寺敷地の南東角に石碑が立つ。
北斗七星の象徴 ”七宮”
この地図をご覧いただきたい。

七宮をオレンジの線でつないでみた。とてもじゃないが北斗七星には見えない。
がしかし、次の画像もご覧いただきたい。

これは、堀越神社境内に鎮座し星まつりが行われる「太上神仙鎮宅霊符神」のシンボルマークである。似ている。七宮の配置は歪ではあるが北斗七星を暗示していると言って差し支えないと感ずる。
そして、四天王寺には道教思想をシンボライズした北斗七星が彫り込まれた「七星剣」が収められていたという。
七星剣、七宮の配置、堀越神社の七夕祭りと鎮宅護符。すべて北斗七星である。これはもはや偶然とは思えない。やはり道教における北辰信仰の影響を受けていると考えざるを得ない。
七宮と道教
道教では、北辰(北極星)が宇宙の全てを支配する唯一神(天帝)であり、その天帝の乗り物ともされる北斗七星は天帝からの委託を受けて人々の行状を監視し、その生死禍福を支配するとされた。
この北辰・北斗を神格化したのが『鎮宅霊符神』すなわち堀越神社の「ちんたくさん」なのである。
そして、『鎮宅霊符神』は神道で天御中主神と習合し、さらには如意輪観音に習合したという。
北辰=鎮宅霊符神=天御中主神=如意輪観音
これらを考え合わせ、四天王寺七宮は北斗に相当するとしたい。守屋の祠を監視しているのだろうか。その象徴として堀越神社に「ちんたくさん」が祀られているのだ。裏鬼門に。
北辰はどこに?
では、北辰(北極星)に相当する場所はどこだろう。

まず直感的に思いついたのが牛王尊である。
七宮のほぼ中心に位置し、守屋の祠を上から抑える位置にあり、四天王寺中央伽藍の鬼門に位置するからである。
しかし、この図をご覧いただきたい。

鬼門の「牛王尊」と裏鬼門にあたる「阿弥陀堂」、堀越神社境内の「ちんたくさん」を結んでみた。紫色のラインである。このライン上に「転法輪石」が存在し、これは神社ライン(オレンジライン)と仏教ライン(イエローライン)の交差点とも一致するのである。
※神社ライン、仏教ラインとは?こちらの記事をご覧頂きたいと存ずる。
(新しいタブで開きます)

こうなってくると、全ての中心は、つまり北辰(北極星)は「転法輪石」なのではないかと考えられるのである。
転法輪とは
では、転法輪が象徴するものとはいったい何だろう。
なんと、
法輪は「煩悩を破壊する仏法の象徴」であり、「如意輪観音」を象徴していたのである。すなわち、転法輪石が天御中主大神であり北辰なのである。
北辰=鎮宅霊符神=天御中主神=如意輪観音=転法輪
七宮まとめ
仏教ラインと道教ライン
物部氏は、饒速日尊、宇摩志麻遅命、から受け継いだ十種神宝を駆使した呪術の使い手である。その党首たる守屋を亡き者とした蘇我氏と太子は、守屋の怨霊を、強烈に恐れたであろうことは想像に難くない。
その怨霊を、四天王を祀ることで封じこめようとした。しかし、それだけでは心もとないので北辰・北斗による守護を求めんがため七宮を建立したわけだ。仏教と道教で怨霊を封じたのである。
神道ライン
では神道ラインはどう考えるか、という課題が残る。
四天王寺の鳥居から真東にラインを引いたとき、そのラインは、生駒山地の麓にある「往生院六蔓寺」を通り、生駒山頂と高安山頂の間を超えて、奈良県大和郡山市矢田の「矢田坐久志玉比古神社」にたどり着くのである。
「六蔓寺」は聖徳太子の叔父にあたる崇峻天皇が建立した寺院であり、その先の「矢田坐久志玉比古神社」は物部氏の祖神とされる饒速日尊を祀る由緒ある古社である。石上神宮が物部氏の総氏神になるまでは、すなわち、四天王寺が建立される前後までは、ここ「矢田坐久志玉比古神社」が物部氏を象徴する神社であったという。
四天王寺の鳥居から、彼岸に昇りくる太陽を崇拝するとき、おのずと、太子殿・守屋の祠・生駒山そして矢田坐久志玉比古神社を崇拝することになる。仏教・道教で怨霊を封じて、神道で崇拝させることで鎮魂を祈る、という構図がみえてきた。
もしかして、太子も、、、
しかし、もっと想像力を膨らませたとき、守屋の祠=物部、生駒山=物部の象徴、矢田坐久志玉比古神社=物部の聖地としたとき、一列に並ぶ他の対象物も物部関連ではないのか?と考えるのである。
一列に並ぶ、その対象物とは、、、「太子殿奥殿」である。
すなわち「太子は物部一族だったのではないか」と。
さらに言えば、七宮が封じ込めているのは守屋の祠だけなのだろうか。先ほどの配置を見ていると、、、
四天王寺が完成する前に太子は謎の死を遂げているのだが。。。
今日のところは、このあたりで終わることとする。
| 「矢田坐久志玉比古神社」の記事はコチラ。実は、この神社がスゴイんです。 ➡ 真実の癒し! 矢田坐久志玉比古神社 |
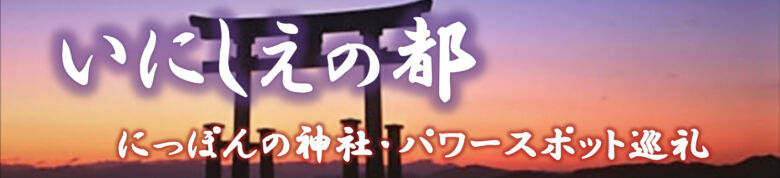









ディスカッション
コメント一覧
はじめまして。
四天王寺では聖徳太子が龍を地下に封じ込めたとされていますが、私の見立てでは、
難波宮(それにまつわる一族)を封印し、それを更に封じるのが四天王寺七宮でしょう。
支配者が滅ぼした一族の祟を恐れ、それを封じ込めたと推測します。
それにしても、聖徳太子関連の施設が異様に多いですが、わざわざ多大な予算を投じて施設を維持するが不自然です。
実在の人物を祀る神社仏閣の殆どは、祟を封じ込め、結界に利用するためではないかと考えています。
ピンバック & トラックバック一覧
[…] https://spiritualjapan.net/1934/ […]