榎木神社(堀川戎神社内)|大阪|だんじり型の本殿がカッコいい。別名「地車稲荷」。

榎木神社は、南森町の阪神高速守口線高架下にある堀川戎神社の境内に鎮座する神社。
鳥居をくぐってすぐ右にある。
こちらは、別名「地車(だんじり)稲荷」とも称される。それは、本殿が地車型だからだ。
また、稲荷神社なのだが、神様のお使いは「狐」ではなく「狸」。
このように、一風変わった「お稲荷さん」である。
榎木神社について
榎木神社 概要
- 所在地 大阪市北区西天満5丁目4番17号(堀川戎神社内)
- 電話番号 06-6311-8626
- 主祭神 句句廼知神、宇迦之御魂神
- 創建年 1838年
- 社格
- 公式HP http://www.horikawa-ebisu.or.jp/
榎木神社 アクセス
MAP
最寄り駅
地下鉄「南森町駅」徒歩6分
駐車場
- なし
榎木神社の祭神とご利益
祭神は「句句廼知神(くくのちのかみ)」と「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」である。
「句句廼知神」は木の精霊と言われる。生命力の向上のご利益を期待したい。
「宇迦之御魂神」は食物の神。五穀豊穣と商売繁盛のご利益を頂ける。
創建と歴史
このあたりの地名「堀川」は、江戸時代初期、慶長3年(1598年)に掘られた運河の名称である。
掘られた当初は、堂島川から北に分岐して扇町あたりが終点の、行き止まりの運河であった。
その堀止あたり(扇町あたり)に大きな榎木が生えていて、人々はその榎木に木の精霊である「句句廼知」が宿っているとし、根元に祠を設けて「句句廼知」を祀った。
これが始まりである。
いつのころからか、その榎木の根元に「吉兵衛」という狸が棲み付いて、毎晩「だんじり囃子」の真似をしていたという。
さて時は流れて、天保9年(1838年)。それまで堀留めだった運河を延長して大川まで開通させることいになった。
その時、その句句廼知を祀る祠は一旦撤去されたが、改めて社殿を造営して立派な神社とした。
これが、榎木神社の創建である。

と同時に、堀川戎神社の境内末社であった「稲生神社」から宇迦之御魂神の別魂(わけみたま)を勧請して榎木神社に合祀した。
よって社名を「稲生神社別魂榎木神社」という長い社名に改名したようだ。
明治40年、神社合併政策によって「榎木神社」は「堀川戎神社」に吸収合併されることになり、堀川戎の境内に遷座。
その時、大きな地車を本殿とした。それはだんじり囃子好きの「狸の吉兵衛」も一緒に遷座してきたと見なしたからなのだろう。粋な計らいである。
それ以降、榎木神社という名称とともに、地車稲荷神社とも称されるようになったという。

地車型の本殿

現在の本殿は地車ではないが、地車型の神殿が造営されている。
そういうわけで、地車稲荷の神使は狐ではなく狸なのである。
願い事が叶うと、その夜に地車囃子が聞こえるとされ、願いが叶ったお礼として地車の模型や絵馬を奉納する習わしとなっている。

合わせて参拝したい近隣の神社
綱敷天神社(大阪市北区神山)
堀川戎神社から北西に700m(15分ぐらい)にある、菅原道真公を祀る古社。
露天神社(大阪市北区曽根崎)
堀川戎神社から真西に800m(15分ぐらい)にある、少彦名命を祀る古社。
縁結びの神様として有名。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
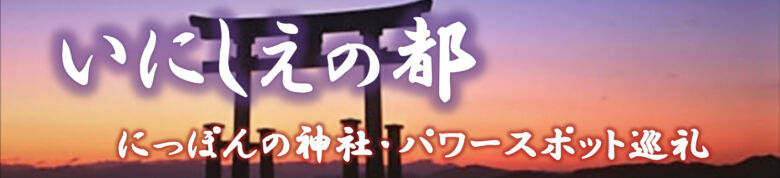








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません