月読命(つくよみのみこと)|三貴神(三貴子)
月読命(つくよみのみこと)は、日本神話に登場する神。
同時に産まれた三貴神であるところの天照大神や建速須佐之男命とちがって、神話内での活躍は無いに等しい。
これは、造化三神における天之御中主神や、木花開耶姫が火中で生んだ三神における火須勢理命にも見える。
これら、三神の真ん中に位置しながら何もしていないように見える神を「無為の神」と呼ぶのは、河合隼雄氏。
その著書「神話と日本人の心」では、日本神話の「中空均衡構造」として、これら「無為の神」が左右にいる両極端な神格の左右への行き過ぎを防ぐ役割を果たしているとする。
この「中空均衡構造」は日本人の心のあり方そのものであり、私は、聖徳太子の十七条憲法の「和をもって貴しとなす」は、その心のあり方を具現化したものではないかと考える。
聖徳太子は仏教に神道の考え方を吹きこんで、「世界の中の日本」の精神的支柱にしようと考えたのではないか?などと考えてみたくなるのであるが、、、
話が逸れた。。。
月読命の概要
月読命の神名
- 月讀命(つくよみのみこと)≪≫古事記
- 月弓尊(つくよみのみこと)≪≫日本書紀
- 月夜見尊(つくよみのみこと)≪≫日本書紀
月読命の神格
- 夜の食国の神・・・伊邪那岐命から命じられた。(古事記)一説には黄泉の国。
- 月の神・・・太陽とともに天を統治するよう命じられた。(日本書紀)
- 海を統治する神・・・伊邪那岐命から命じられた。(日本書紀)須佐之男命とかぶる。
- 占いの神・・・亀トの術を日本に伝えた壱岐氏が奉祭する神である。
月読命の神徳
壱岐の月讀神社によると、、、
月読み、すなわち暦や潮の干満など、月が関わるすべての行いに対してご神徳をもつという。
- 生命の誕生(安産、健康、病気平癒)
- 漁業の繁栄(航海安全、大漁)
- 農業の誕生(自然界では旧暦の暦と共にある)
- 商売繁盛
月読命の系譜
古事記を参考に、月読命の系譜を記載しておく。
- 父 ≫≫ 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)
- 母 ≫≫ なし
- 姉 ≫≫ 天照大神(あまてらすおおみかみ)
- 弟 ≫≫ 建速須佐之男命(たてはやすさのおのみこと)
月読命が登場する神話
前述の通り、月読命が登場する神話はほとんどない。
三貴子の誕生
伊邪那岐命が黄泉国から帰還して、身に付いた穢れを洗うために禊を行った。その禊によって、住吉三神や綿津見三神をはじめとする多くの神々が生まれた。
そして最後に、、、
最後に顔を洗ったとき、三柱の神々が生まれた。
- 左目を洗うと「天照大御神」が生まれた。
- 右目を洗うと「月読命」が生まれた。
- 鼻を洗うと「建速須佐之男命」が生まれた。
伊邪那岐命は「最後に三柱の貴い子を得たり!」と喜び、それぞれに役割を与えた。
- 天照大御神に「御倉板挙之神」(みくらたなののかみ)という首飾りの玉の緒を渡して高天原を委任した。
- 月読命には夜の食国を委任した。
- 建速須佐之男命には海原を委任した。
月読命の誕生 異伝(日本書紀)
日本書紀の「異伝」をご紹介しよう。
伊弉諾尊が
- 左の手に白銅鏡を取り持って大日孁尊(天照大神)を生み、
- 右の手に白銅鏡を取り持って月弓尊(月読命)を生む。
- そして、首を回してよそ見をしている時に素戔鳴尊が生まれた。
なんと、須佐之男命はよそ見をしている時にうまれたのか。。。
保食神との対面(日本書紀)
天照大神から保食神に合うよう命じられた月読命は、地上に降りて保食神のもとを訪問した。
これを歓迎しようと、保食神は口から食べ物を出して、月読命を迎えた。
これを見た月読命は「なんと穢らわしい!」と怒って、保食神を剣で刺し殺してしまう。
保食神の死体から、牛馬や蚕、稲などが生れ、これが穀物の起源となる。
この月読命の所業知った天照大神は、「汝悪しき神なり!顔も見たくない!」と怒り、太陽と月は半日ごとに現れるようになった。これが昼と夜の起源である。
この神話と同じ内容の神話が、古事記では「須佐之男命」が「大気都比売神」(おほげつひめ)を刺殺すという設定で描かれている。
- 日本書紀における神格「海を統治する神」が須佐之男命と重複していること、
- 保食神との神話が、古事記では同じ内容で、主人公が須佐之男命に入れ替わっていること、
- 天照大神と月読命は、左右の目・左右の手・日と月というように、対照的存在として描かれている。
など、元々は天照大神と月読命の二柱の神による伝承に、あとから須佐之男命を付け加えたのではないかといった説が出るほどである。
しかしそうなると、中間的存在「無為の神」はむしろ須佐之男命であるべきなのに、どうして月読命なのだろうか。。。
月読尊を祀る神社(当ブログ内)
月読神社(京都市右京区)

壱岐国の月読神社から勧請された「月の神」を祀る神社。
大依羅神社(大阪市住吉区)

祭神八座の二座目に神名があげられてる。筆頭は大己貴命。
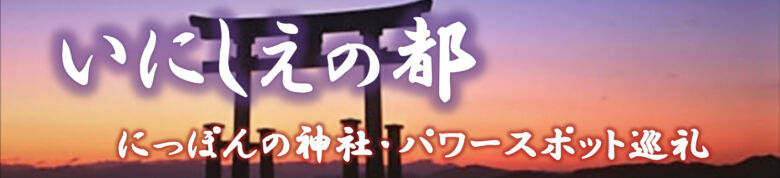




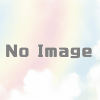


ディスカッション
コメント一覧
中間的存在「無為の神」はむしろ須佐之男命であるべきなのに、どうして月読命なのだろうか。私は「無為の神」ではないと思っています。その人の考え方次第ですが、須佐之男命こそよく分かりませんが…須佐之男命様あまり好きでは無いですか?私は大好きです、太陽、月、金星神とも、今回台風14号防いでくれました、伊勢湾台風以上と言われた台風を…その代わり、高千穂峡の遊歩道はじめ被害が出ましたが…それに過去には、京都に原子爆弾第三候補になっていたのを防いだとも、あそこは八坂神社がありますし。ただ、いざという時仕事し、普段は仕事されないので分からないですが…それに、疫病払いの神様とも、それも信じるか信じないかはあなた次第ですが…
ソダシ様
コメント、ありがとうございます!
今後ともよろしくお願いします!